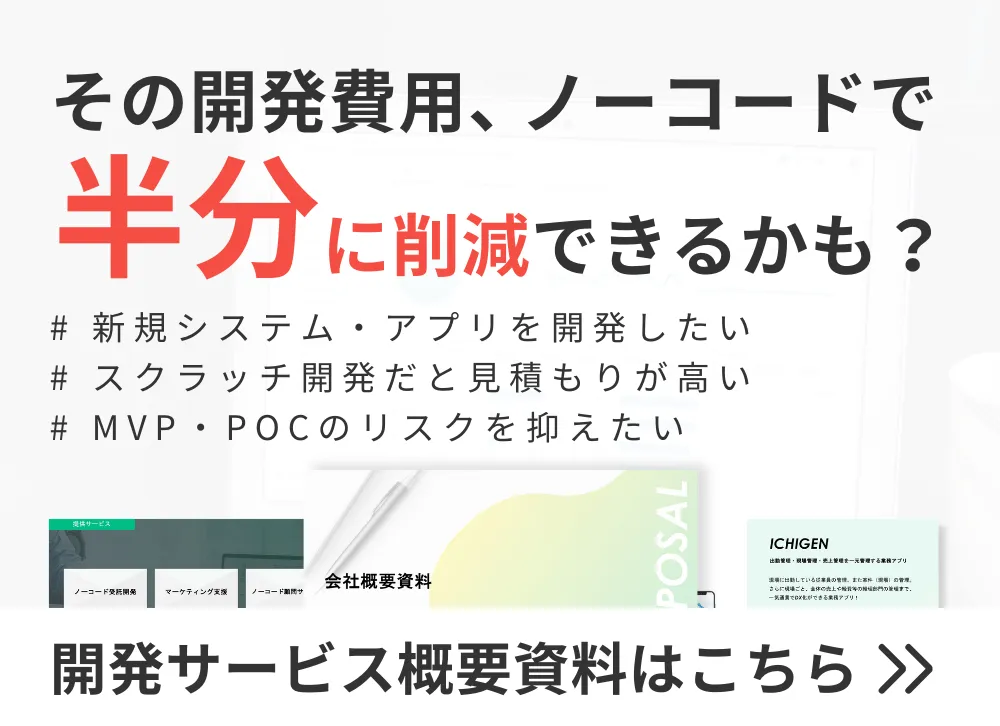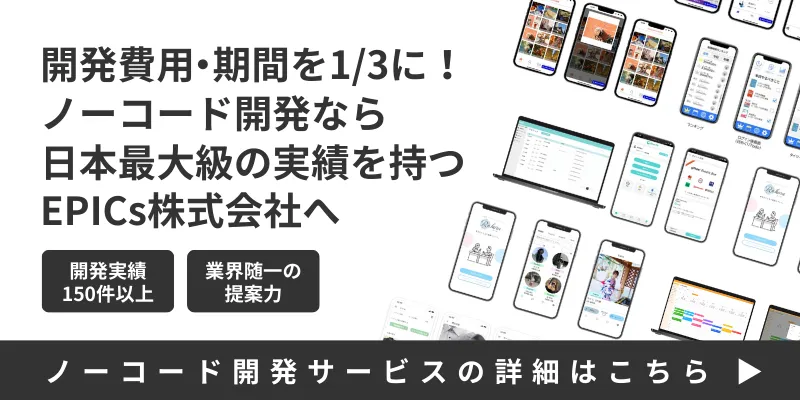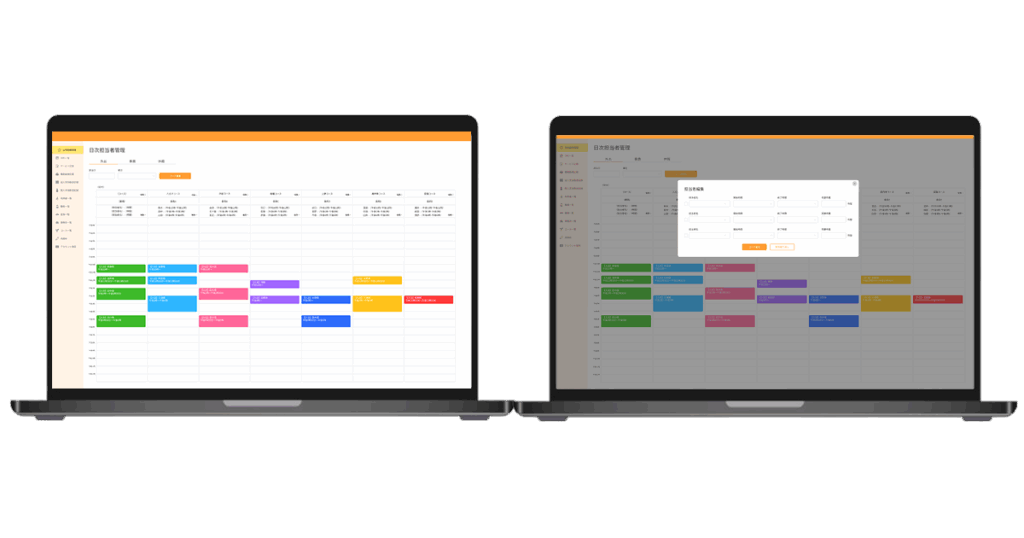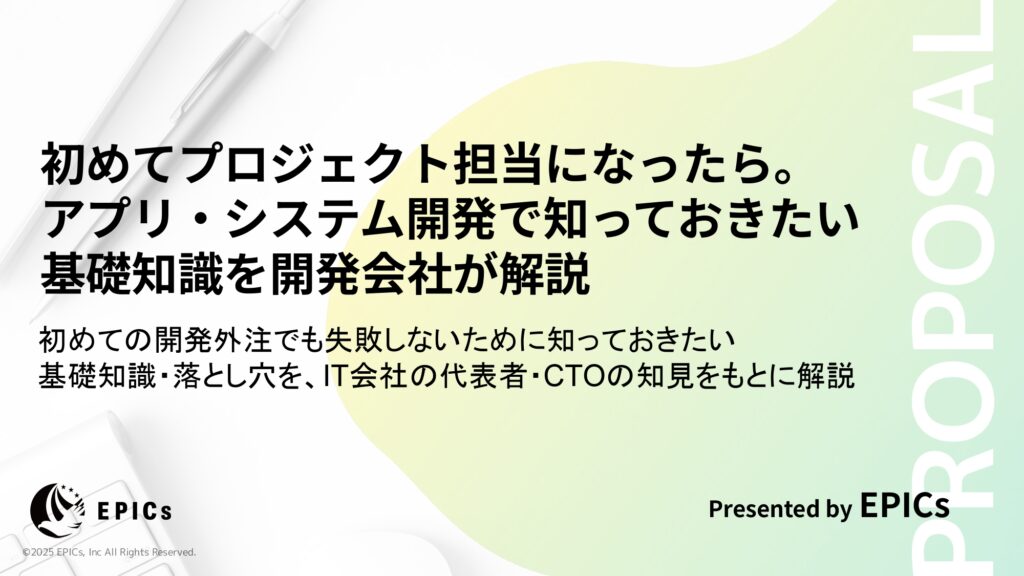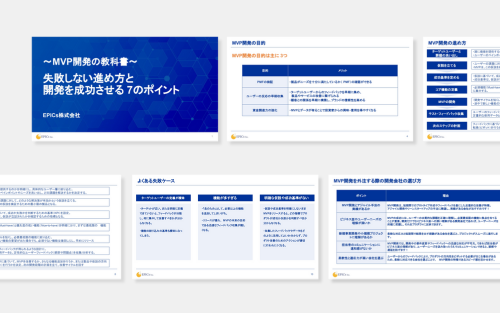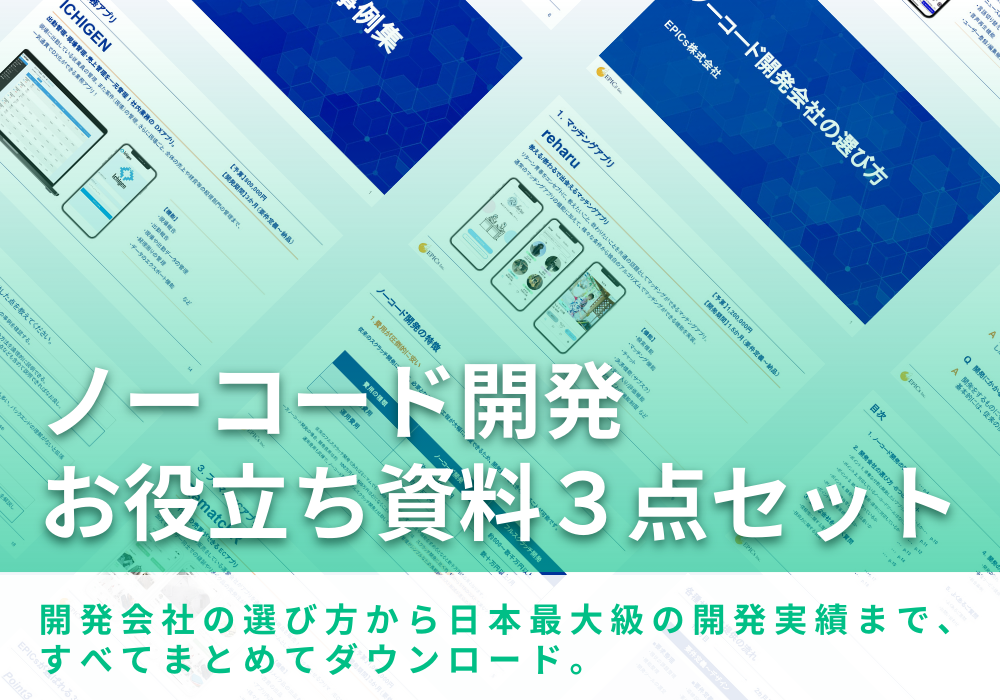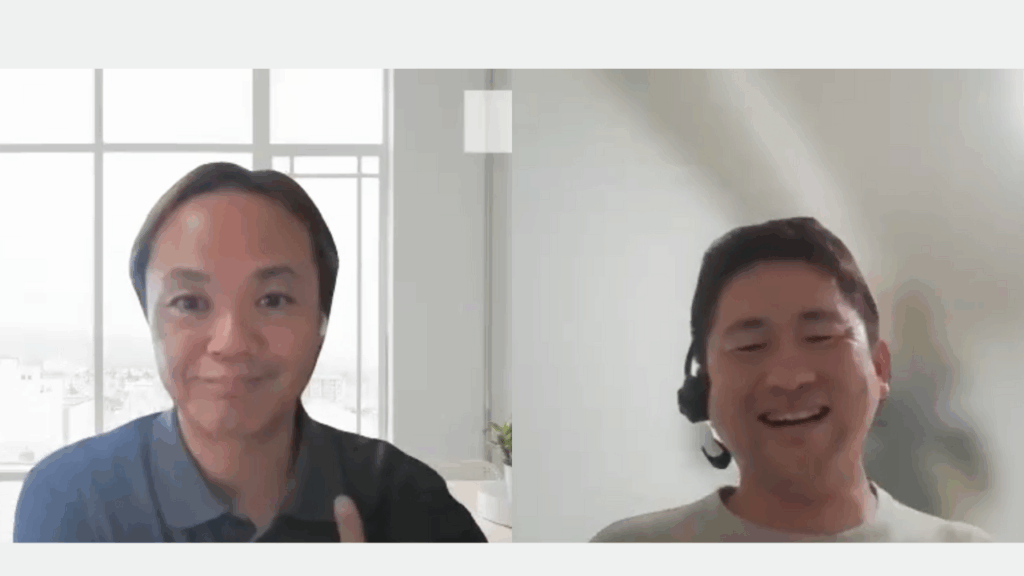PoC開発のおすすめ会社16選!開発会社の選び方やコストを抑える方法も解説
新規事業の立ち上げやDXプロジェクトにおいて、まず小規模で概念実証を行う「PoC(Proof of Concept)」が重要な第一歩となります。
しかし、適切な開発会社を選ばなければ、貴重な時間と予算を無駄にしてしまうリスクがあります。
本記事では、費用対効果、技術力、業界特化性など、様々な観点から厳選したPoC開発会社16社をご紹介。
それぞれの特徴や適用ケースを詳しく解説し、開発会社の選び方や開発コストを抑える方法もお伝えします。
EPICs株式会社は、ノーコードツールを使った開発で最短2週間・最安30万円でPoC開発を実現可能です。
複数のノーコードツールを使い分けることで、従来手法よりも開発費用と開発期間の大幅な削減を実現し、開発後のマーケティング支援まで一貫してサポートいたします。
1. 目的別に最適なPoC開発会社の見極め方 低コスト・AI特化・量産移行・超高速プロトタイピング・業界特化の5カテゴリから16社を厳選。開発期間や技術領域、予算規模で比較することで、自社の検証目的に最適なパートナーを選定できます。
2. PoC開発費用を30〜50%削減する具体的手法 ノーコード開発で期間を1/5に圧縮、オフショア開発で人月単価を半減(日本80万円→ベトナム40万円)など、300万円以下の小規模PoCを実現する実践的なコスト削減策が分かります。
3. PoC→本開発の移行率4%を突破する成功条件 96%が本格導入に至らない現実を踏まえ、移行実績の確認方法・スケーラビリティ設計の依頼ポイント・PoC疲れを防ぐ体制評価の3つの視点で、検証で終わらせない会社選びができます。
低コストで小規模から相談できるPoC会社
予算を抑えながらも質の高いPoCを実現したい企業向けに、以下の3社をご紹介します。
- Sun Asterisk
- Fusic
- CO-WELL Japan
株式会社Sun Asterisk

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Sun Asterisk |
| 最大の特徴 | 1,000名規模のベトナム開発拠点でMVPを超短納期・低単価実装 |
| どんなケースにおすすめか | 新規事業を“数百万円×2-3か月”で試したい |
株式会社Sun Asteriskは、ベトナムと日本のハイブリッド体制により、圧倒的な低コストでのPoC開発を実現している会社です。
1,000名規模のベトナム開発拠点を活用することで、人月単価を大幅に抑制しながら、高品質なMVP(最小実行可能製品)を短期間で提供しています。
同社の強みは、透明性の高い方法論にあります。
DXやMVPに関する記事を多数公開しており、開発プロセスが明確に示されているため、依頼者も安心してプロジェクトを進められます。
また、既に上場を果たしており、資本基盤も安定している点も大きな魅力。
特に新規事業を数百万円の予算で2-3か月という短期間で検証したい企業にとって、Sun Asteriskは理想的なパートナーといえるでしょう。
コストパフォーマンスとスピードを重視する案件では、他社に引けを取らない実力を発揮します。
株式会社Fusic

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Fusic |
| 最大の特徴 | AWS・生成AIを活かした“低コストRAG PoC”支援 |
| どんなケースにおすすめか | 生成AIを安価に検証し、横展開も視野に入れたい |
株式会社Fusicは、生成AIとAWSを組み合わせた低コストPoCに特化した開発会社です。
特にRAG(Retrieval-Augmented Generation)という技術を活用したPoCにおいて、従来の半分程度のコストで実現できる独自のアプローチを持っています。
PoCでPineconeを採用することで、費用を約50%圧縮する実績を残しています。
同社は200件を超えるIoT×AI案件の豊富な経験を持ち、実践的なノウハウが蓄積されています。
また、自社イベントを定期的に開催し、最新の生成AI事例を積極的に共有する姿勢も評価できるポイント。
技術トレンドへの感度が高く、常に最新の手法を取り入れています。
EPICs株式会社CTO 石森裕也からのコメント
開発現場の実感として、RAGは「社内文書を学習させたChatGPTのようなもの」と理解すると分かりやすいです。実務では、マニュアル検索の自動化や過去の問い合わせ履歴からの回答生成などで活用されています。ただしRAGの精度は、元となるデータの整理度に大きく依存します。弊社が関わったプロジェクトでは、RAG導入前のデータクレンジング(データの整理・修正作業)に想定の2倍の時間がかかったケースもあります。「すぐに使える綺麗なデータがある」という前提で進めると、検証自体が頓挫するリスクがあるため注意が必要です。
株式会社CO-WELL Japan

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社CO-WELL Japan |
| 最大の特徴 | ベトナムオフショア×日本QAで高品質・低単価 |
| どんなケースにおすすめか | 既存EC/業務システムを低コストで早く試作 |
株式会社CO-WELL Japanは、ベトナムでの開発と日本での品質保証を組み合わせた独自のハイブリッドモデルで、高品質かつ低コストなPoC開発を提供しています。
平均人月36万円未満という明確な価格設定を公表しており、予算計画が立てやすいのが特徴です。
同社の強みは、ECサイトや業務システムといった実用的なシステム開発における豊富な実績にあります。
自社ブログでMVPとPoCの違いについて詳しく解説するなど、顧客の理解促進にも積極的に取り組んでいます。
また、ベトナムオフショア開発でありながら、日本でのQA(品質保証)体制を整えることで、品質面での不安を解消しています。
既存のECサイトや業務システムの機能拡張を低コストで試作したい企業や、実用性を重視したPoCを短期間で実現したい企業にとって、CO-WELL Japanは頼りになるパートナーです。
コストを最重要視する案件では、特に威力を発揮するでしょう。
AI・データ領域に強いPoC会社
最先端のAI技術やデータ活用に特化したPoC開発を求める企業向けに、以下の3社をご紹介します。
- Preferred Networks(PFN)
- ABEJA
- ExaWizards
株式会社Preferred Networks

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Preferred Networks |
| 最大の特徴 | 世界トップクラスDL研究×産業実装 |
| どんなケースにおすすめか | 製造AIや自律ロボットで最先端を狙う |
株式会社Preferred Networksは、世界最高レベルのディープラーニング研究と産業実装を両立する、日本を代表するAI企業です。
トヨタやファナックといった製造業界のトップ企業との共同PoC実績を多数持ち、理論と実践の両面で圧倒的な実力を誇っています。
同社の最大の武器は、独自開発のスーパーコンピュータ「MN-シリーズ」による高速学習環境。
これにより、他社では時間のかかる大規模なAI学習を短期間で完了させることが可能です。
また、Chainerをはじめとする研究成果をオープンソースで公開するなど、AI業界全体への貢献姿勢も評価されています。
製造業における品質管理AI、自律走行ロボット、産業用IoTなど、最先端技術を駆使したPoCを検討している企業には、PFNが最適な選択肢となります。
費用は高めですが、技術力と実績において他の追随を許さない圧倒的な優位性を持っています。
株式会社ABEJA
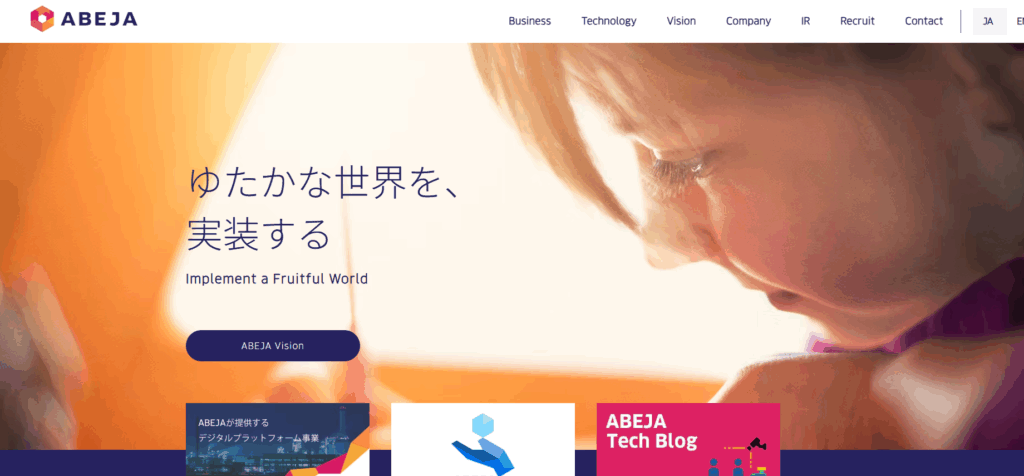
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ABEJA |
| 最大の特徴 | 200社超のAI導入×Human-in-the-LoopでPoC突破率向上 |
| どんなケースにおすすめか | 流通・小売の画像解析を短期に実運用へ |
株式会社ABEJAは、200社を超えるAI導入実績を持つ、実用化に特化したAI企業です。
同社が掲げる「ゼロPoC」というコンセプトは、PoCで終わらせずに必ず運用まで持っていくという強い意志を表しており、実際に高いPoC突破率を実現しています。
Human-in-the-Loop(人間参加型AI)の手法により、AIの精度向上と実用性を両立させています。
技術基盤の強さも注目ポイント。
NVIDIAやGoogleといった世界的IT企業からの出資を受けており、最新のAI技術へのアクセスと安定した開発環境を確保しています。
特に画像認識分野では、月額課金制のSaaSサービスも提供しており、導入ハードルの低さも魅力です。
流通・小売業界での画像解析AI(商品認識、在庫管理、顧客行動分析など)を短期間で実運用レベルまで持っていきたい企業には、ABEJAが理想的なパートナーとなります。
PoCから本格運用まで一気通貫でサポートしてくれる体制が整っています。
株式会社エクサウィザーズ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社エクサウィザーズ |
| 最大の特徴 | 独自exaBaseで生成AI/RAGを迅速デモ |
| どんなケースにおすすめか | 企業横断AI基盤を短期PoC→本番 |
株式会社エクサウィザーズは、独自開発のAI基盤「exaBase」を武器に、生成AIやRAG(検索拡張生成)を活用したPoCを迅速に提供する企業です。
三井不動産の「リハウスAI査定」をはじめとする大手企業との実績を持ち、企業レベルでのAI活用において確かな実力を発揮しています。
同社の特徴は、業界別にカスタマイズされたテンプレートを豊富に保有していることです。
介護、金融、不動産など、各業界特有の課題とニーズを深く理解しており、より実用的なPoCを短期間で実現できます。
また、RAG PoCの導入手順を公開するなど、技術の透明性と顧客理解の促進にも積極的。
複数部門や子会社を抱える企業で、AI基盤を横断的に活用したいケースや、生成AIを使った新しいサービスを短期間でPoC検証したい企業には、ExaWizardsが最適です。
業界知識と技術力を兼ね備えた提案を期待できます。
「ノーコード開発会社の選び方」「EPICs株式会社 ノーコード開発の実績集」
「ノーコード受託開発サービスの特徴」が同梱されたお役立ち資料セット。
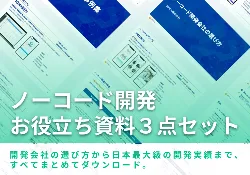
量産移行まで伴走するPoC会社
PoCから本格運用、さらには全社展開まで一貫してサポートを求める企業向けに、以下の3社をご紹介します。
- TIS
- NTTデータ
- 日立ソリューションズ
TIS株式会社
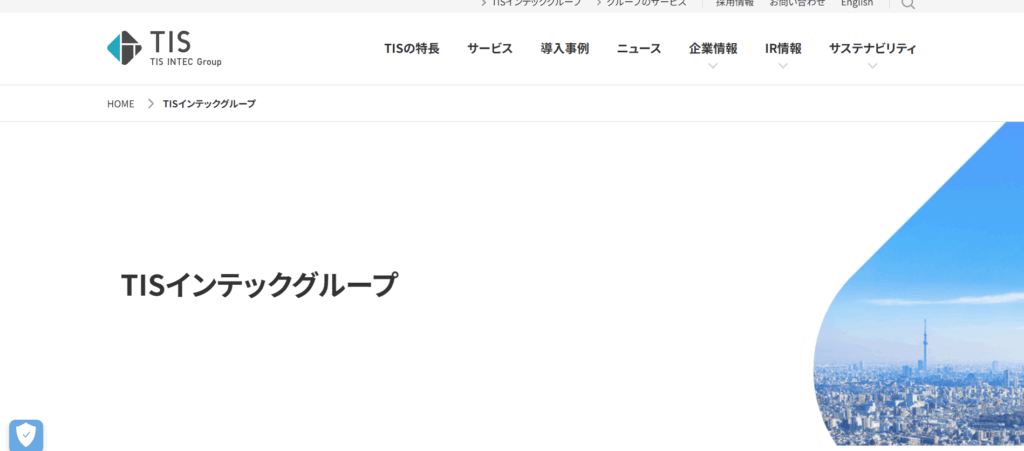
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | TIS株式会社 |
| 最大の特徴 | 生成AI基盤×事業共創でPoC→量産をワンストップ |
| どんなケースにおすすめか | 大規模DXを段階拡張しながら内製化したい |
TIS株式会社は、PoCから量産運用まで一貫したサポート体制を誇る大手システムインテグレーター。
同社独自の「デジタル基盤オファリング」により、PoC用の環境を即日で提供できる点が大きな強みです。
これにより、アイデア段階から実証実験まで、従来では考えられないスピードでの展開が可能になっています。
特筆すべきは事業共創プログラムの存在。
単なる技術提供にとどまらず、事業計画の策定から市場分析、収益モデルの構築まで、ビジネス面でのサポートも充実しています。
国内最大級のSI企業としてのリソースを活かし、小規模なPoCから大規模なシステム構築まで、あらゆる段階に対応可能です。
大企業で段階的にDXを推進し、最終的には内製化を目指したい企業には、TIS株式会社が理想的なパートナーとなります。
技術力だけでなく、事業戦略面でのサポートも期待でき、長期的な成功を見据えた取り組みが可能です。
株式会社NTTデータ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社NTTデータ |
| 最大の特徴 | フェーズ戦略で小さく始め全社展開まで伴走 |
| どんなケースにおすすめか | データ利活用を部門→全社に広げたい |
株式会社NTTデータは、独自のTDF-AM(段階的拡張モデル)を活用した戦略的なPoC展開を得意とする企業です。
小さな部門レベルでの実証実験から始まり、成功事例を積み重ねながら全社レベルまで段階的に拡張していくアプローチを提唱しています。
この手法により、リスクを最小限に抑えながら確実な成果を上げることが可能です。
同社の強みは、公共機関や金融機関といった高い信頼性が求められる分野での豊富な実績。
長年培ってきたセキュリティノウハウと運用保守体制は業界トップクラスを誇ります。
また、グローバル70カ国での展開実績があり、海外展開を視野に入れた企業にとっても頼りになる存在です。
データ利活用を特定部門から始めて全社に展開したい大企業や、高いセキュリティレベルが要求される業界の企業には、NTTデータが最適な選択肢となります。
安定性と拡張性を両立した提案を期待できるでしょう。
株式会社日立ソリューションズ
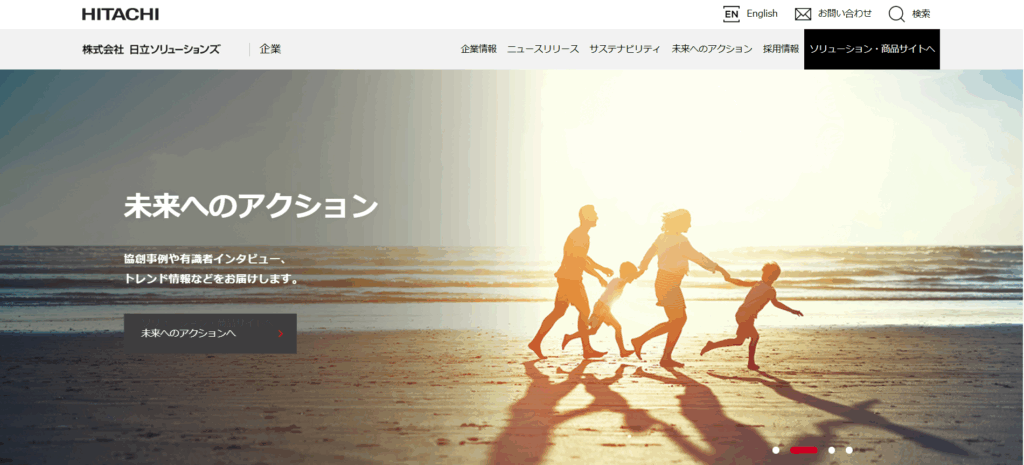
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社日立ソリューションズ |
| 最大の特徴 | API基盤/ブロックチェーンをPoC→内製化まで支援 |
| どんなケースにおすすめか | 既存SIを活かしつつ新技術を早期事業化 |
株式会社日立ソリューションズは、既存システムを活かしながら新技術を段階的に導入していくアプローチを得意とする企業です。MuleSoft連携PoCによるAPI内製化支援や、Web3分野でのPoC→運用保守まで一貫したサービス提供など、幅広い技術領域をカバーしています。
同社の特徴は、実証実験で終わらせない徹底したサポート体制。PoCで技術的な有効性を確認した後、本格的なシステム構築、さらには運用保守まで、長期的な視点でプロジェクトを支援します。また、データ利活用プラットフォームも一括で提供できるため、複雑なシステム構成でも統合的な管理が可能です。
既存のシステムインフラを有効活用しながら、API連携やブロックチェーンといった新技術を段階的に導入したい企業には、日立ソリューションズが適しています。安定した運用実績と新技術への対応力を兼ね備えた提案が魅力です。
超高速プロトタイピングが得意なPoC会社
スピード重視でUIやUXの検証を素早く行いたい企業向けに、以下の3社をご紹介します。
- EPICs株式会社
- Goodpatch
- GNUS
- GeNEE
EPICs株式会社

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | EPICs株式会社 |
| 最大の特徴 | 日本最大級のノーコード開発実績で 最短2週間・最安30万円を実現 |
| どんなケースにおすすめか | 極限まで開発期間と費用を抑えてアイデアを形にしたい |
表2(評価軸スコア)
EPICs株式会社は、ノーコード開発において日本最大級の実績を持つ開発会社です。
最短2週間、最安30万円というスピードとコストパフォーマンスで、アイデア段階からプロトタイプまでを一気に実現しています。
従来の開発手法では数ヶ月かかっていたPoCを、ノーコードツールを駆使することで劇的に短縮することが可能です。
同社の最大の強みは、複数のノーコードツールに対応していること。
作りたいシステムの要件に応じて最適なツールを選択できるため、開発期間の短縮と費用削減を同時に実現しています。
また、単なる開発にとどまらず、マーケティング支援も提供。
アプリやシステムを作って終わりではなく、実際に市場で成功するまでの伴走サポートが受けられる点も大きな魅力です。
 大熊滉希
大熊滉希限られた予算と時間の中で、とにかく早くアイデアを形にして市場の反応を確認したいスタートアップや、新規事業の初期検証を低リスクで進めたい場合は、EPICs株式会社へご相談ください。
ノーコード開発の特性を最大限活かした効率的なPoC実現をいたします。
株式会社グッドパッチ
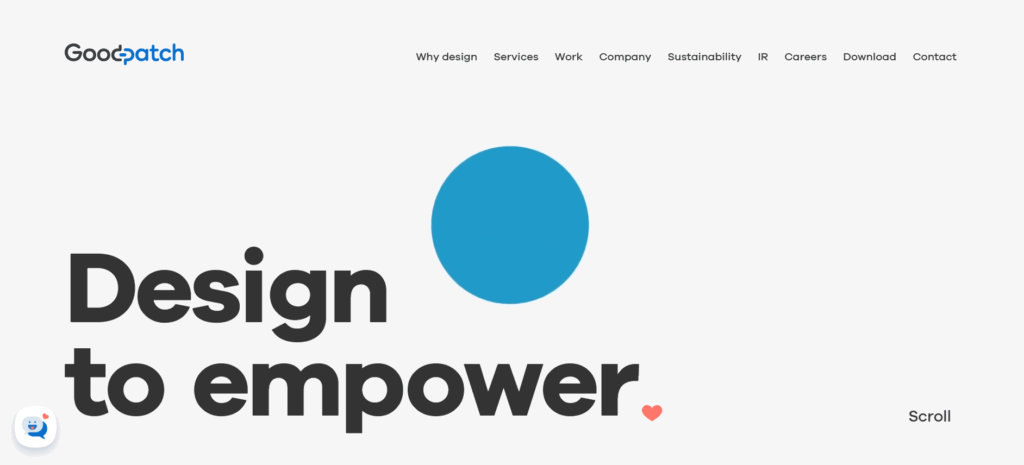
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社グッドパッチ |
| 最大の特徴 | Prott等自社ツールでUIプロトを即日共有 |
| どんなケースにおすすめか | UX検証を1〜2週間で回したいスタートアップ |
株式会社グッドパッチは、自社開発のプロトタイピングツール「Prott」を活用した超高速UIプロトタイプ制作を得意とする企業です。
「Rapid Prototyping(高速プロトタイピング)」を標榜し、アイデアから動作するプロトタイプまでを即日で共有できる体制を整えています。
これにより、従来では数週間かかっていたUI検証サイクルを大幅に短縮可能です。
同社の実績は大手企業からスタートアップまで400件を超える多様な案件を手がけており、様々な業界のUX課題に対する深い理解を持っています。
また、DX人材育成のためのワークショップも提供しており、クライアント企業の内製化支援にも積極的に取り組んでいます。
UI/UXの仮説検証を短期間で繰り返したいスタートアップや、ユーザー中心設計のアプローチでサービス改善を図りたい企業には、Goodpatchが最適です。
デザイン思考とアジャイル開発を組み合わせた効率的なプロセスを提供してくれます。
株式会社GNUS
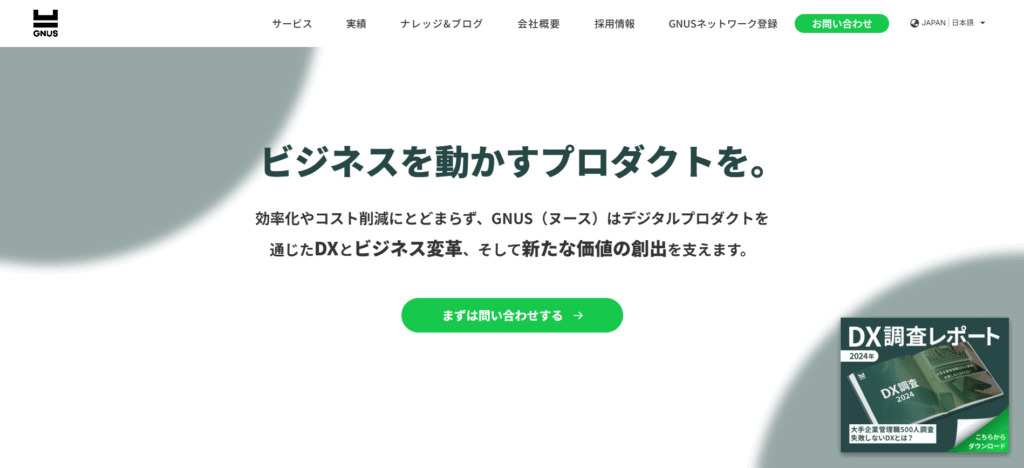
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社GNUS |
| 最大の特徴 | エンジニア×BizDev混成チームで仮説検証高速 |
| どんなケースにおすすめか | SaaS新機能を数週間で体験版公開したい |
株式会社GNUSは、エンジニアとビジネス開発担当者が混成チームを組み、事業構想から実装まで一気通貫で推進する独自のアプローチを持つ企業です。
技術面だけでなくビジネス面での検証も同時に進めることで、より実用的で市場価値の高いPoCを短期間で実現しています。
同社の強みは、ノーコードツールとの連携による初期実装コストの抑制。
複雑な機能は本格開発で対応しつつ、基本機能はノーコードで素早く実装することで、開発期間とコストの両方を最適化しています。
また、早期のUXテストを前提としたイテレーション(反復改善)プロセスにより、ユーザーフィードバックを効率的に取り入れることが可能です。
SaaSサービスの新機能を数週間という短期間で体験版として公開し、ユーザーの反応を見ながら本格開発を進めたい企業には、GNUSが理想的なパートナーとなります。
スピードとコストパフォーマンスを重視する案件で威力を発揮するでしょう。
株式会社GeNEE

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社GeNEE |
| 最大の特徴 | MVP専門チームが企画-要件-開発を一気通貫 |
| どんなケースにおすすめか | Web/アプリのβ版を超短期リリースしたい |
株式会社GeNEEは、MVP(最小実行可能製品)開発に特化した専門チームを持つ企業です。
企画段階から要件定義、そして実際の開発まで、一気通貫でのサポート体制を整えており、クライアントの負担を最小限に抑えながら超短期でのβ版リリースを実現しています。
同社の特徴は、MVP専用プランを明確に公表し、価格とサービス内容の透明性を確保していること。
これにより、予算計画が立てやすく、スタートアップや中小企業でも安心して依頼することができます。
また、企画段階から伴走することで、後戻りや手戻りを大幅に削減し、効率的な開発プロセスを実現しています。
Webサービスやモバイルアプリのβ版を可能な限り短期間でリリースし、市場の反応を早期に確認したい企業には、GeNEEが適しています。
東京本社での対面ミーティングも可能なため、密なコミュニケーションを重視するプロジェクトでも安心です。
MVP開発において、スピードと品質のバランスを取った提案を期待できます。
業界課題に精通した専門特化型PoC会社
特定業界の課題解決に特化した技術とノウハウを持つ企業向けに、以下の3社をご紹介します。
- SORACOM
- Terra Drone
- Connected Robotics
株式会社ソラコム
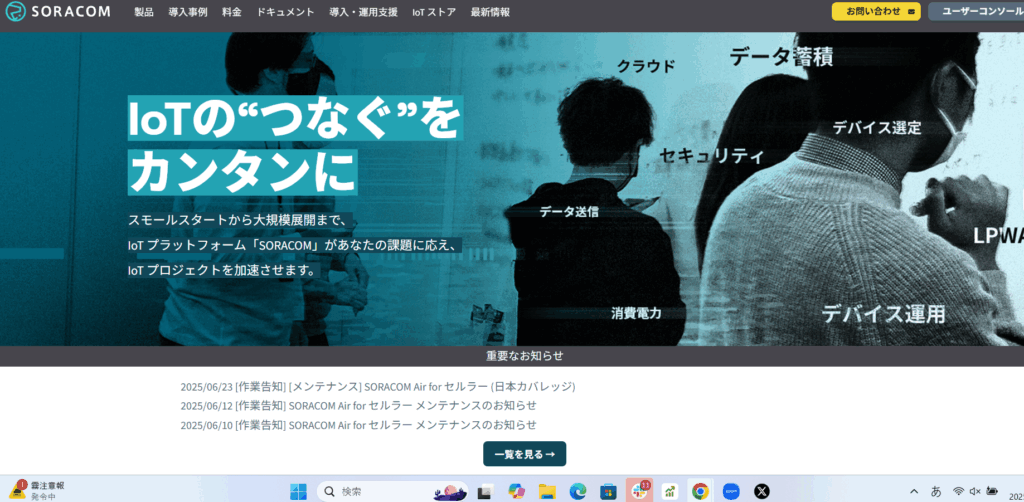
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ソラコム |
| 最大の特徴 | IoT通信PF×PoCツール群で現場課題を即検証 |
| どんなケースにおすすめか | センサーデータを早期に可視化しROIを測りたい |
株式会社ソラコムは、IoT通信プラットフォームとPoC専用ツール群を組み合わせた独自のアプローチで、現場課題の即座な検証を可能にしている企業です。
PoCパッケージを活用することで、SIMカードとダッシュボードを即日で開通でき、センサーデータの収集から可視化まで、驚くほど短時間で実現できます。
同社の強みは、製造業、農業、物流といった多様な業界での豊富な導入事例を持っていること。
各業界特有の課題を深く理解しており、現場のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
また、AWS出身のメンバーが多数在籍しており、クラウドとの親和性も非常に高く、スケーラブルなシステム構築を前提とした設計が期待できます。
工場の設備監視、農地の環境モニタリング、物流トラッキングなど、センサーデータを活用したIoTシステムの有効性を早期に検証したい企業には、SORACOMが最適です。
ROI(投資対効果)の測定も含めた総合的なサポートを受けることができるでしょう。
Terra Drone株式会社

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | Terra Drone株式会社 |
| 最大の特徴 | ドローン×AI点検を国内外でPoC→導入 terra-drone.netterra-drone.net |
| どんなケースにおすすめか | インフラ点検を空・3Dデータ化したい |
Terra Drone株式会社は、ドローン技術とAIを組み合わせたインフラ点検ソリューションの分野で、国内外において圧倒的な実績を誇る企業です。
送電線の3Dマッピングによる点検PoCを成功させるなど、従来の人力点検では困難だった高所や危険箇所での精密な検査を実現しています。
同社の大きな特徴は、海外20拠点での現地対応が可能な点です。
これにより、日本国内だけでなく、アジア・太平洋地域での展開を視野に入れた企業にとって、非常に心強いパートナーとなります。
また、Terra Inspectioneeringによる石油タンク点検など、重要インフラの維持管理において実証済みの技術力を持っています。
電力、石油・ガス、通信インフラなどの点検業務を空撮データと3D技術で効率化したい企業や、従来の点検方法では限界のある高所・危険箇所の検査を自動化したい企業には、Terra Droneが理想的な選択肢です。
グローバル展開も視野に入れた長期的な戦略を立てることができるでしょう。
コネクテッドロボティクス株式会社
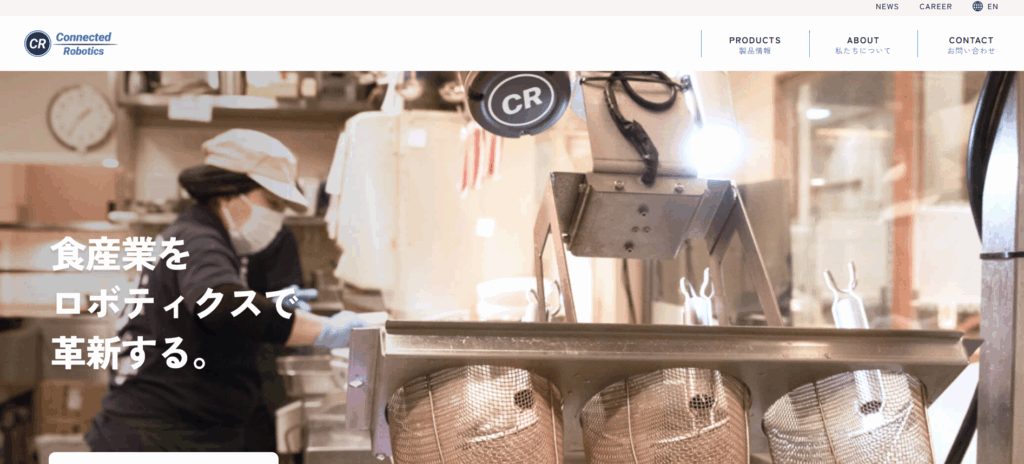
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | コネクテッドロボティクス株式会社 |
| 最大の特徴 | 調理ロボットの実地PoCで厨房DXを推進 |
| どんなケースにおすすめか | 外食/コンビニの省人化を検証したい |
コネクテッドロボティクス株式会社は、調理ロボットを活用した厨房DX(デジタルトランスフォーメーション)の実証実験において、業界をリードする企業です。
同社が開発する「Octo Chef」をはじめとする複数の調理ロボットを実際の店舗環境で稼働させ、省人化効果や運用コストの検証を行っています。
同社の信頼性を示すのが、東京都のPoC Groundへの採択実績や、業務用厨房機器大手のホシザキとの資本提携です。これにより、単なる技術開発にとどまらず、量産体制の構築まで見据えた本格的な事業展開が可能になっています。
また、公共機関との連携により、社会実装に向けた取り組みも積極的に進めています。
外食チェーンやコンビニエンスストアなど、人手不足が深刻化している飲食業界で省人化を検討している企業には、Connected Roboticsが最適なパートナーとなります。
実際の店舗環境での実証実験を通じて、導入効果を定量的に測定できる点が大きな魅力です。
厨房オペレーションの効率化と品質向上を両立したい企業にとって、非常に価値のある提案を期待できるでしょう。
POC開発の費用相場と予算別の開発会社選び
POC開発の費用は、プロジェクトの規模や技術難易度によって大きく変動します。「要問い合わせ」で終わる情報サイトが多い中、実際の意思決定では具体的な予算枠が決まっているケースがほとんどです。
ここでは、予算帯別に選ぶべき開発会社のタイプと、費用を左右する要素について解説します。
- 小規模PoC(300万円以下)を狙う
- 人月単価と開発期間を逆算
- オフショア開発で30-50%削減
小規模PoC(300万円以下)を狙う
POC開発の標準的な費用相場は、期間1-3ヶ月で300万円から3,000万円の範囲となります。特に生成AIを活用したPOCの場合、月額120万円から、期間2-4ヶ月が一般的な相場です。
矢野経済研究所の「DX市場調査2024」によると、国内のAI・PoC開発市場は2024年に前年比32.8%成長し、市場規模は約4,200億円に達すると予測されています。特に生成AI関連のPoC需要が急増しており、2025年には市場全体の40%以上を占める見込みです。
出典 デジタルトランスフォーメーション(DX)市場に関する調査 / 株式会社矢野経済研究所 / 2024年
初めてPOCに取り組む企業や、予算が限られている中小企業には、300万円以下の小規模POCから始めることをおすすめします。重要なのは「必要最小限の機能」での検証に絞り込むこと。完璧な製品を作ることがPOCの目的ではなく、仮説を検証することに焦点を当てるべきです。
MVP(Minimum Viable Product、実用最小限の製品)開発という考え方を活用することで、フルスケール開発の5分の1の期間に圧縮できます。たとえば、在庫管理システム全体を作るのではなく、「特定の商品カテゴリーの需要予測機能のみ」に絞ってPOCを実施するといったアプローチが効果的です。
費用を抑えるもう一つの方法は、ノーコード・ローコード開発に強い会社を選ぶことです。これらの開発手法では、プログラミングをほとんど行わずに、視覚的なツールを使ってシステムを構築できるため、開発期間とコストを大幅に削減できます。
 大熊滉希
大熊滉希ノーコード・ローコード特化型の開発会社では、300万円以下でのPOC実施も可能になります。
人月単価と開発期間を逆算
POC開発の見積もりを理解するには、「人月単価」という考え方を知っておく必要があります。人月単価とは、1人のエンジニアが1ヶ月働いた場合の費用を指し、AI開発では月額100万円から250万円が相場です。
POC開発は大きく2つのプロセスに分かれます。計画プロセスでは、目的の策定や検証方法の設定を行い、自社で実施する場合は30-100万円程度、外注する場合は100-240万円程度の費用がかかります。実証プロセスでは、MVP開発や実際の検証を行い、自社実施で50-100万円程度、外注で100-240万円程度が目安となります。
ここで注目すべき重要なデータがあります。「3ヶ月を超えるPOCは成功率が3分の1に低下する」という調査結果です。具体的には、3ヶ月以内のPOCは成功率65%ですが、3-6ヶ月では35%、6ヶ月以上では15%まで下がってしまいます。
IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」でも、PoC実施企業のうち「3ヶ月以内に検証完了した企業」の本格導入率が最も高く、検証期間が長期化するほど導入断念率が上昇すると報告されています。同調査では、PoC長期化の要因として「目的の曖昧さ」「評価基準の未設定」が上位に挙げられています。
出典 DX白書2023 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) / 2023年
長期化の主な原因は「スコープクリープ」と呼ばれる現象です。最初は在庫管理の検証だったのが、いつの間にか全社システムの刷新になっているといったケースが該当します。期間とコストを明確に設定し、それを厳守する体制を持った開発会社を選ぶことが成功への鍵となります。
見積もりを依頼する際は、「何人月で、どこまでの範囲を検証するのか」を明確にしてもらいましょう。
EPICs株式会社CTO 石森裕也からのコメント
普段PoC開発を行っている身としては、スコープクリープの背景には「ステークホルダーの増加」があると感じています。PoCが進むにつれ、当初関与していなかった部門から「うちの要件も入れて欲しい」という声が上がり、検証範囲が広がってしまうパターンです。弊社では、PoC開始前に「検証しないことリスト」を明文化し、関係者全員で合意を取ることを推奨しています。たとえば「既存システムとの連携は本開発フェーズで対応」「多言語対応は今回のPoCでは除外」といった形で明記します。これにより3ヶ月以内での完了率を大幅に改善できています。
オフショア開発で30-50%削減
開発コストをさらに抑える有力な選択肢として、オフショア開発があります。オフショア開発とは、海外の開発拠点を活用してシステム開発を行う手法で、特にベトナムやインドが人気の開発拠点となっています。
ベトナムオフショア開発を例に取ると、日本のエンジニアの月額単価が約80万円であるのに対し、ベトナムのエンジニアは約40万円と、30-50%のコスト削減が可能です。近年、ベトナムのIT技術は目覚ましい発展を遂げており、人件費は高騰傾向にありますが、それでも日本と比較すれば大幅なコストメリットがあります。
JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)の「オフショア活用実態調査2023」では、ベトナムオフショア開発を活用した企業の87.3%が「コスト削減効果があった」と回答しており、平均削減率は35.2%と報告されています。ただし同調査では、コミュニケーションコスト増加により期待したコスト削減効果が得られなかった企業も14.6%存在することが指摘されています。
出典 ソフトウェア開発におけるオフショア活用の実態調査 / 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) / 2023年
株式会社C-UNIT SQUAREのように、日本に本社を置きながらベトナムのホーチミンに開発拠点を設立している企業では、要件定義やUI/UX設計を日本のマルチスキルスタッフが担当し、開発作業を各専門分野に特化したベトナムスタッフが行うという共創関係を構築しています。
POCのような短期間プロジェクトでも、ラボ型開発という契約形態に対応する会社を選ぶことで、柔軟なリソース調整が可能になります。ラボ型開発では、専属のエンジニアチームを確保する形態で、2-3名の小規模からスタートし、プロジェクトの進捗に応じて100名規模まで拡大した実績もあります。
EPICs株式会社CTO 石森裕也からのコメント
私たちの開発経験から、オフショア開発は「要件が明確に固まっているシステム」には適していますが、「試行錯誤しながら作るPoC」には向かないケースが多いと感じています。特にUI/UXの細かい調整や、ビジネスロジックの頻繁な変更が必要な場合、コミュニケーションコストが想定以上にかかります。実際に弊社がサポートしたあるスタートアップでは、当初オフショア開発を検討していましたが、「週3回以上の仕様変更が想定される」という状況だったため、国内のノーコード開発に切り替えた結果、開発期間を半分に短縮できました。オフショア開発は「コスト削減」だけでなく、「自社の要件固まり度」で判断すべきです。
POC開発後の本格導入を見据えた会社の選び方
POCの真の目的は、検証で終わることではなく、事業化・本稼働につなげることにあります。しかし、「PoC疲れ」「PoC止まり」という言葉が示すように、POCは成功したのに本格導入に進まないケースが多発しているのが現実です。
本格導入を見据えた会社選びでは、以下の3つの視点が重要になります。
- PoC→本開発の移行率を確認
- スケーラビリティ設計を依頼
- PoC疲れ防止の体制を評価
PoC→本開発の移行率を確認
POC開発会社を選ぶ際、最も重要な指標の一つが「PoC→本開発の移行率」です。三菱電機インフォメーションシステムズが実施した調査では、衝撃的なデータが明らかになっています。PoCを経て本格導入に至ったのは、わずか4%しかありませんでした。
内訳を見ると、POC実施後に中断となった案件が17%、机上検討段階で消滅した案件が41%という結果です。一方で、POCの段階を踏まずに本格導入となったものも10%存在しており、「検証のための検証」に陥っているケースが多いことが分かります。
三菱総合研究所の「AI・データ利活用に関する企業実態調査2022」でも同様の傾向が報告されており、AI・データ分析プロジェクトのうち、PoC段階で終了した案件は全体の約6割に達しています。移行できなかった主な理由として「投資対効果の不明確さ」(42.3%)、「業務プロセスへの組み込みの困難さ」(38.7%)が挙げられています。
内訳を見ると、POC実施後に中断となった案件が17%、机上検討段階で消滅した案件が41%という結果です。
出典 AI・データ利活用に関する企業実態調査 / 三菱総合研究所 / 2022年
開発会社を選ぶ際は、必ず「POC→本開発の移行実績」を確認しましょう。具体的には、以下のような質問が有効です。
- 過去3年間で、POCプロジェクトは何件実施し、そのうち何件が本格導入に至ったか
- POCで作成したプロトタイプやルールを、本番環境でそのまま活用できた事例はあるか
- POC段階で使用した技術スタックは、本番環境でも継続して使えるものか
「使い捨て技術」を避けることも重要です。POC専用の簡易的なツールやフレームワークで検証を行い、本番開発では全く異なる技術で一から作り直すというケースでは、POCのコストが無駄になってしまいます。
EPICs株式会社CTO 石森裕也からのコメント
開発現場で見てきた経験から、移行率が低い最大の理由は「PoCの成功基準が曖昧」だったケースです。「AIの精度80%以上」といった技術的指標だけで判断し、「実際の業務でどれだけ使われるか」という運用面の検証が抜けていることが多いです。弊社が関わったある製造業のプロジェクトでは、PoC段階で「週に何回、誰が、どのタイミングで使うか」まで具体的にシミュレーションし、現場の担当者3名に2週間実際に使ってもらいました。その結果、使いにくいポイントが早期に明確になり、本開発への移行がスムーズに進みました。PoCは技術検証だけでなく、「現場で使われる仕組みか」を検証する場でもあるべきです。
スケーラビリティ設計を依頼
スケーラビリティとは、システムの拡張性を意味します。POCは小規模に始めるべきですが、設計段階から将来の全社的なニーズを考慮した拡張性設計が不可欠です。
たとえば、POC段階では10人のユーザーで検証していたシステムが、本番環境では1,000人が同時に使用する必要があるケースを考えてみましょう。スケーラビリティを考慮していない設計では、本番移行時に全面的な作り直しが必要となり、結果的にコストと時間が膨大にかかってしまいます。
POC段階でエンタープライズレベル(大企業規模)の利用状況をシミュレートし、負荷時のパフォーマンスを検証しておくことが望ましいです。SCSK株式会社の事例では、POCの評価指標として以下の6つを設定することを推奨しています。
- 機能・性能(求める機能が実現できるか、性能要件を満たすか)
- 費用(初期費用と運用費用が予算内に収まるか)
- メンバースキル(既存の技術者で運用できるか、新たな教育が必要か)
- 移行(既存システムからのデータ移行は可能か)
- スケジュール(本番導入までのスケジュールは現実的か)
- 標準化(業界標準や社内標準に準拠しているか)
さらに、既存の基幹システムとの連携も重要な検証ポイントです。CRM(顧客管理システム)、データウェアハウス、BIツールなど、企業が既に保有しているシステムとの統合ポイントを事前に特定できる会社を選びましょう。
 大熊滉希
大熊滉希POC段階でこれらの主要な統合ポイントをテストしておくことで、本格導入後のスムーズな連携が実現できます。
PoC疲れ防止の体制を評価
「PoC疲れ」「PoC貧乏」という言葉をご存知ですか。これは、検証を何度も繰り返すだけで本格的な開発ステップに進むことなく、コストと時間だけがかかってしまう状態を指します。特にAIやIoTなどの新技術を導入する際に陥りやすい問題です。
三菱総合研究所の分析によると、PoC疲れの一因は「AIの特徴を理解しないままPoCに臨んでいること」にあります。AIの精度が十分であっても、業務課題の明確化や導入効果の試算が正しく行われていないために、POCが失敗しているケースが多いのです。
PoC疲れを防ぐには、開発会社が以下の体制を持っているかを評価することが重要です。
明確なゴール設定のサポート POCを「あくまで仮説検証のためのステップ」と位置づけ、具体的な数値目標を設定する支援ができるか。「業務を効率化したい」ではなく、「問い合わせ対応の時間を20%削減する」といった定量的な目標設定ができるかがポイントです。
効果起点のAI評価の実施 技術的な実現可能性だけでなく、「どれだけの業務効果が得られるか」を起点として評価する体制があるか。机上の計算ではなく、実際の業務データを使った費用対効果の試算を行える会社を選びましょう。
目標達成後の動きまで設計 POCで目標を達成した後、どのように本格開発に移行するかまで、最初の段階で設計されているか。株式会社ベンジャミンのように、POCの結果を踏まえて本格的なシステム開発や導入フェーズに進む際の継続的なサポート体制を持つ会社は、PoC疲れに陥るリスクが低くなります。
現場と経営層、システム開発者の間で認識のズレが生じないよう、定期的なコミュニケーションの場を設定する体制も重要です。
 大熊滉希
大熊滉希PoCを繰り返しているうちにプロジェクトのゴールが曖昧になることを防ぎ、常に「なぜこのPOCを実施しているのか」を全員が共有できる環境を作れる開発会社を選びましょう。
PoC開発ならEPICs株式会社
スピードとコストパフォーマンスを重視したPoC開発なら、ぜひEPICs株式会社をご検討ください。
日本最大級のノーコード開発実績を活かし、最短2週間・最安30万円という業界トップクラスの条件でPoCを実現いたします。
従来の開発手法では数ヶ月かかるプロジェクトも、複数のノーコードツールを使い分けることで劇的な期間短縮が可能。
お客様の要件に最適なツールを選択し、無駄のない効率的な開発を行います。
また、システム開発だけでなく、マーケティング支援も提供しているため、作って終わりではなく、実際に市場で成功するまでの伴走サポートが受けられます。
限られた予算でアイデアを素早く形にしたいスタートアップ様や、新規事業の初期検証を低リスクで進めたい企業様に最適なソリューションを提供いたします。
1からの開発も、途中からの開発も、お気軽にEPICsにご相談ください!