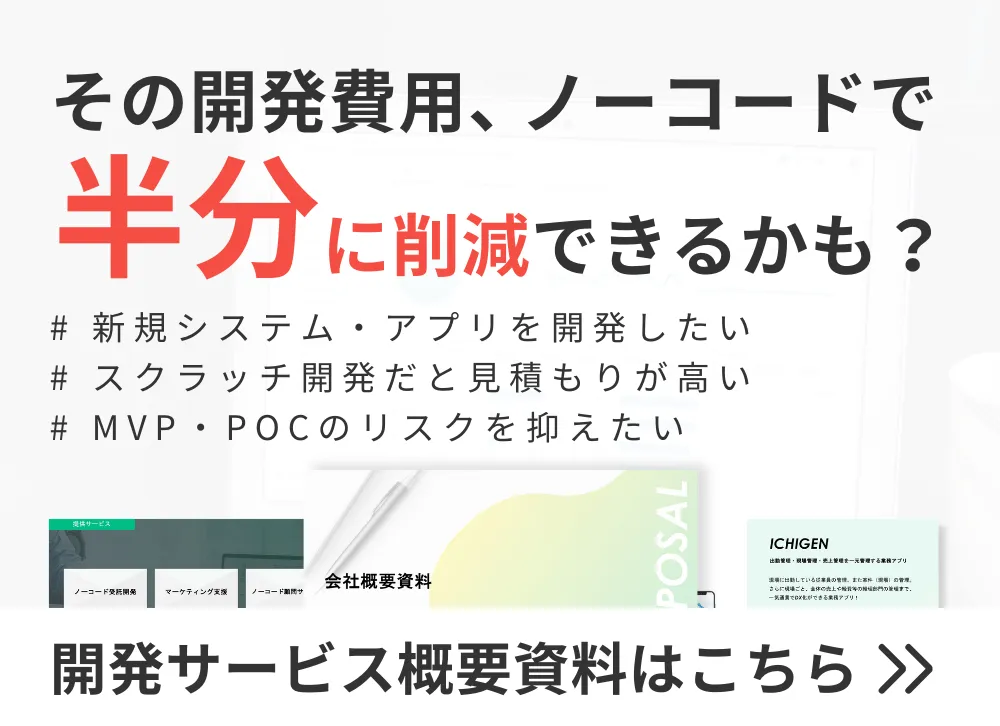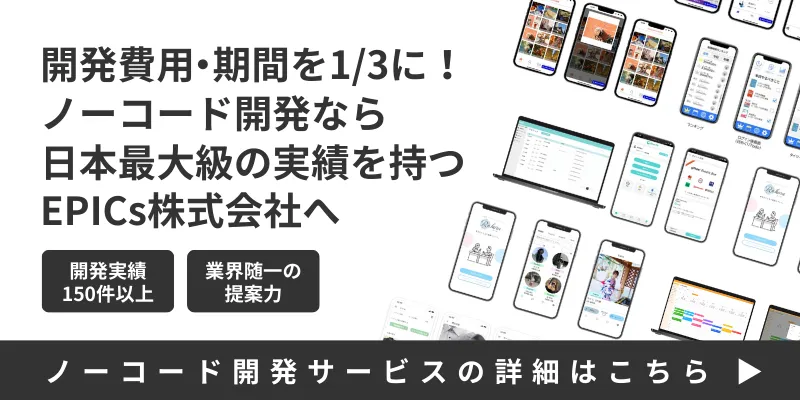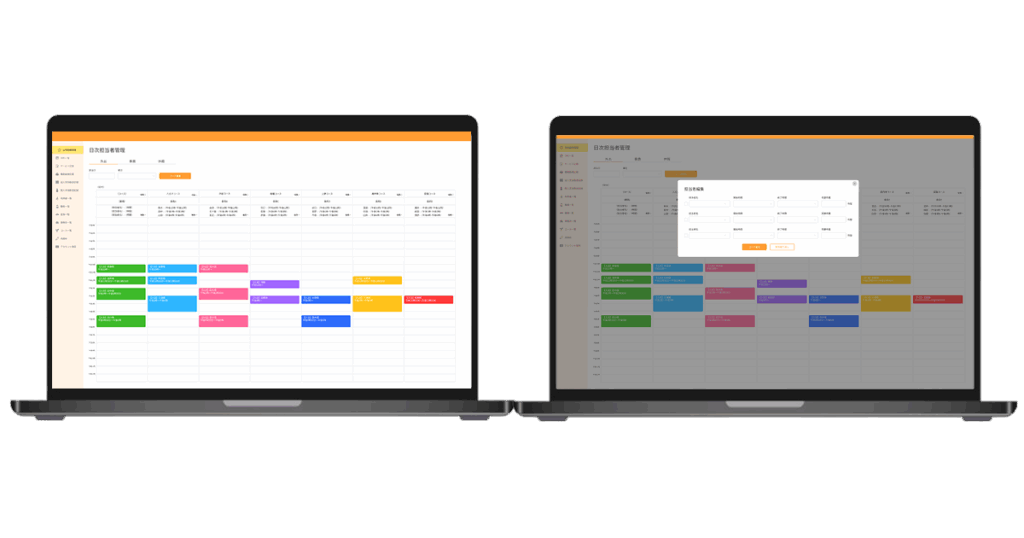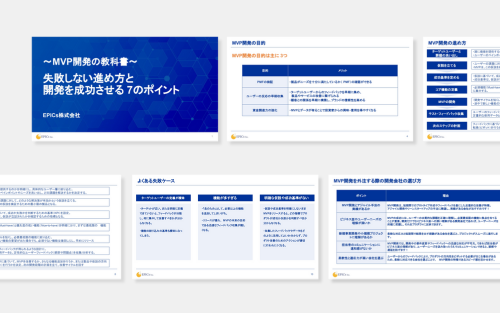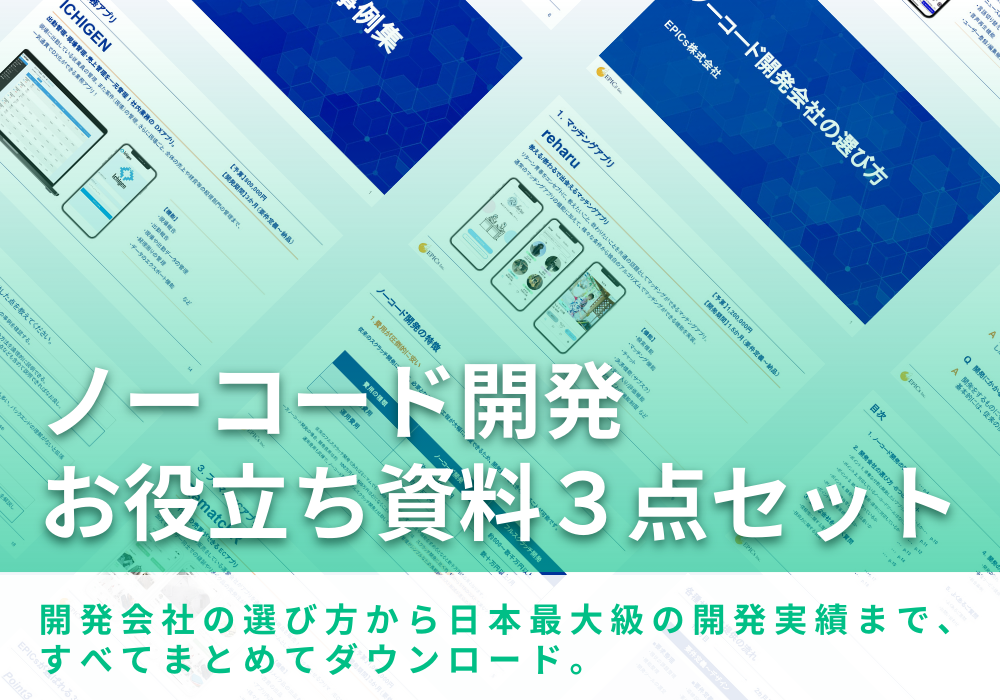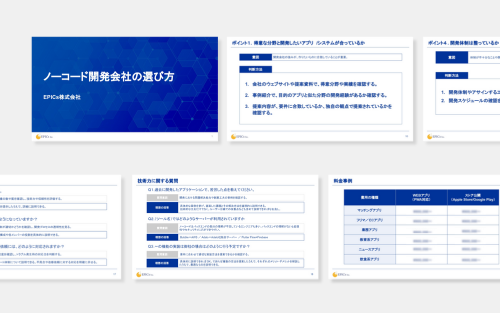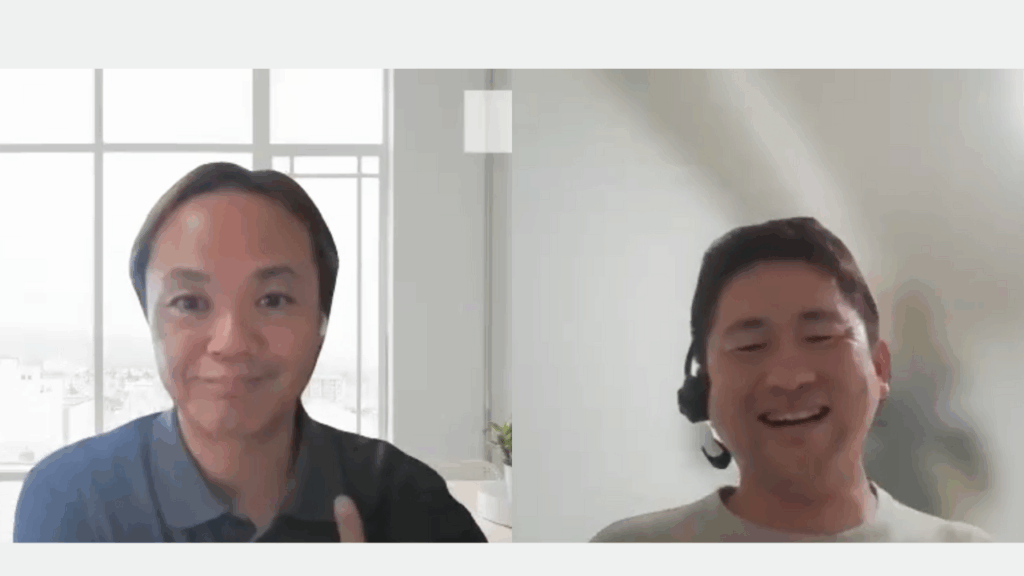医療システムの開発費用相場を徹底解説!コスト削減のポイントも紹介
こんにちは!
EPICs株式会社です。
業務システムは、医療機関でも導入が進んでおり、患者さんの情報管理や業務効率化のためのシステムとして現代の医療現場には欠かせないものとなっており、システム導入を検討されている方も多くいらっしゃいます。
しかし、開発したいシステムは開発費用がどれくらいかかるのかという点が気になるところだと思います。
この記事では、医療システムの開発費用相場について詳しく解説し、開発費用を抑えるポイントや開発会社の選び方もご紹介しています。
医療システムの導入を検討の場合は、是非ご参考ください。
【結論】医療システムを安く開発するならノーコード
結論から申し上げると、医療システムの開発コストを抑えたいなら「ノーコード開発」がおすすめです!
ノーコードとは、プログラミングの知識がなくても、視覚的な操作でアプリやシステムを作成できる開発手法のことで、多くの医療システムはこのノーコード開発で十分対応可能です。
従来のプログラミングによる開発であるスクラッチ開発と比較すると、ノーコード開発では費用を約1/3程度に抑えられます。
近年のノーコードツールは機能が充実しており、患者管理や予約システム、簡易的な電子カルテまで作成できるものもあります。
ノーコード開発は導入スピードも速く、カスタマイズも比較的しやすいという特徴もあります。
 大熊滉希
大熊滉希初期コストと運用コストの両面で効率化が図れるため、医療システムを
安く開発したい場合は、ノーコード開発の検討をおすすめします。
医療システムの開発費用相場・料金
医療システムの開発費用は、規模や機能によって大きく異なります。
ここでは、システムの規模別に費用相場を解説します。
最低限の機能なら60万円〜
| 開発方法 | 初期費用 |
| ノーコード開発 | 60万円〜80万円 |
| スクラッチ開発 | 200万円〜250万円 |
最低限の機能を持つ医療システムとは、一般的には以下のような機能が含まれます。
- 患者基本情報の登録・管理
- 予約管理の基本機能
- 簡易的な会計処理
- 基本的なレポート出力
このレベルのシステムであれば、ノーコード開発の場合は60万円程度から開発可能です。
対してスクラッチ開発では200万円前後が相場となり、約3倍以上の費用差が生じます。
 大熊滉希
大熊滉希最低限の機能はノーコードでも十分開発が可能ですので、ノーコード開発を行うことで費用を安く、開発期間を短くしてシステムを導入できます。
通常のアプリなら120万円〜
| 開発方法 | 初期費用 |
| ノーコード開発 | 120万円〜180万円 |
| スクラッチ開発 | 400万円〜600万円 |
通常レベルの医療システムには、最低限の機能に加えて以下のような機能が含まれます。
- 電子カルテの基本機能
- 処方箋発行システム
- 診療報酬請求(レセプト)対応
- 在庫管理機能
- 他システムとの基本的な連携
このクラスのシステムになると、ノーコード開発では120万円〜180万円程度が相場となります。一方、スクラッチ開発では400万円〜600万円ほどかかるケースが多く、やはり3〜4倍の費用差があります。
通常レベルのシステムは、中規模のクリニックや診療所で幅広く採用されています。
 大熊滉希
大熊滉希この規模のシステムであれば、日常業務のほとんどをカバーできます。
そしてこの規模もノーコード開発で十分対応可能な機能が多く、コスト効率の良い選択肢と言えます。
高度な機能・大規模なら300万円〜
| 開発方法 | 初期費用 |
| ノーコード開発 | 300万円〜500万円 |
| スクラッチ開発 | 1,000万円〜1,500万円以上 |
高度な機能を持つ大規模な医療システムとは、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 高度な電子カルテ(画像管理含む)
- 複数診療科対応
- 高度な医療機器との連携
- AIによる診断支援
- 複数拠点間でのデータ共有
- 詳細な分析レポート機能
このレベルになると、ノーコード開発でも300万円〜500万円程度の費用が必要になります。
スクラッチ開発では1,000万円〜1,500万円以上かかることも珍しくありません。
大規模病院や専門性の高い医療機関では、このクラスのシステムが求められるケースが多いです。
高度な機能でもノーコード開発で多くの機能は対応できますが、より高度で複雑なロジックが必要になる機能だと開発に限界があり、スクラッチ開発との併用などが必要となります。
 大熊滉希
大熊滉希システムを適切に設計し、ノーコード開発とスクラッチ開発を組み合わせることができれば、従来のフルスクラッチ開発と比較して大幅なコスト削減が可能です。
「ノーコード開発会社の選び方」「EPICs株式会社 ノーコード開発の実績集」
「ノーコード受託開発サービスの特徴」が同梱されたお役立ち資料セット。
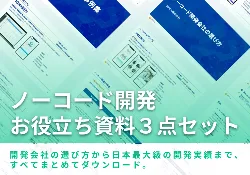
医療システムの開発以外にかかる費用
医療システムを導入する際は、開発費用だけでなく、その他にもさまざまな費用がかかります。
医療システムの開発以外にかかる主な費用項目は以下のとおりです。
- 運用保守に関する費用
- レセプト関連費用
- セキュリティ対策費用
- インフラ費用
- 新機能・修正の開発費用
運用保守に月額2万円〜
医療システムは導入してからが本番です。
安定して使い続けるためには、定期的な保守やメンテナンスが欠かせません。
運用保守費用には主に以下のようなものが含まれます。
- システムの監視・障害対応
- セキュリティアップデート
- 技術サポート(電話・メール対応)
- 定期的なバックアップ
- 法改正対応
 大熊滉希
大熊滉希月額の運用保守費用は、システムの規模や契約内容によって異なりますが、一般的にはノーコード開発の場合で月額2万円〜5万円程度、スクラッチ開発の場合で月額5万円〜10万円程度が相場となっています。
レセプト関連費用に月額1万円〜
医療機関特有の費用として忘れてはならないのが「レセプト関連費用」です。
レセプトとは診療報酬明細書のことで、保険診療を行う医療機関では必須の業務となっています。
レセプト関連費用には以下のようなものが含まれます。
- レセプトソフト(レセコン)の利用料
- オンライン請求システムの利用料
- レセプト点検サービス費用
- 診療報酬改定時の更新費用
レセプト関連費用は月額1万円〜3万円程度が相場です。
電子カルテと一体型のシステムを選ぶと、別々に導入するよりもコストを抑えられる場合があります。
また、診療報酬改定(通常2年に一度)の際には、システム更新費用として追加で5万円〜10万円程度かかることも念頭に置いておきましょう。
 大熊滉希
大熊滉希保険診療を行う医療機関にとって、レセプト業務は収入に直結する重要な業務です。
システム選定の際には、単に費用の安さだけでなく、操作性やサポート体制も含めて総合的に判断することをおすすめします。
セキュリティ対策費用に年間20万円〜
医療システムで扱う患者情報は極めて機密性の高い個人情報です。
2023年4月からは医療機関へのサイバーセキュリティ対策が義務化されており、適切なセキュリティ対策は必須となっています。
セキュリティ対策費用には以下のようなものが含まれます。
- ウイルス対策ソフトのライセンス費
- ファイアウォール設置・運用費
- データ暗号化ツール費用
- セキュリティ監査・脆弱性診断費用
- スタッフ向けセキュリティ教育費用
セキュリティ対策費用は、医療機関の規模によって大きく異なりますが、小規模クリニックでも年間20万円〜50万円程度は見ておくべきでしょう。大規模病院ではさらに高額になります。
 大熊滉希
大熊滉希サイバー攻撃による情報漏洩は、金銭的損失だけでなく、患者からの信頼喪失にも繋がります。
セキュリティ対策は「コストではなく投資」と考え、適切な予算を確保することが重要です。
インフラ費用に初期30万円〜+月額費用
医療システムを稼働させるためには、適切なインフラ環境が必要です。
インフラ費用には主に以下のようなものが含まれます。
- サーバー機器(オンプレミス型の場合)
- ネットワーク機器(ルーター、スイッチなど)
- クライアント端末(パソコン、タブレットなど)
- ネットワーク回線費用
- バックアップ装置
インフラ費用は導入するシステムの形態によって大きく異なります。
オンプレミス型の場合、サーバー機器などの初期費用として30万円〜100万円程度、加えて電気代や設置スペースのコストがかかります。
一方、クラウド型では初期費用は抑えられますが、月額利用料として1万円〜5万円程度が必要です。
また、パソコンやタブレットなどの端末は医療機関の規模や運用形態によって必要台数が変わってきます。
1台あたり10万円〜20万円程度として計算し、必要台数を掛け合わせると良いでしょう。端末の耐用年数は通常4〜5年程度なので、定期的な更新費用も考慮に入れておく必要があります。
 大熊滉希
大熊滉希ネットワーク回線については、安定性を重視して、可能であればバックアップ回線の確保も検討すべきです。
月額のネットワーク費用として1万円〜3万円程度を見込んでおきましょう。
新機能・修正の開発費用
医療システムは導入後も、法改正や業務フローの変更、新たなニーズの発生などに応じて、機能追加や修正が必要になることがあります。
新機能・修正の開発費用は、内容によって大きく異なりますが、一般的には以下のような費用感覚です。
- 軽微な修正:5万円〜10万円程度
- 中規模な機能追加:20万円〜50万円程度
- 大規模な機能拡張:50万円〜100万円以上
ノーコード開発の場合は、自院でカスタマイズできる範囲も多いため、比較的低コストで対応できることが多いです。
一方、スクラッチ開発の場合は、より柔軟な対応が可能である反面、費用も高くなる傾向があります。
 大熊滉希
大熊滉希新機能追加や修正について、年間予算として開発費用の10〜20%程度を見込んでおくと良いでしょう。
例えば、初期開発費用が300万円のシステムであれば、年間30万円〜60万円程度の予算を確保しておくイメージです。
医療システムの開発費用に影響する主な要素
医療システムの開発費用は、さまざまな要素によって変動します。
適切な予算計画を立てるためには、これらの要素を理解しておくことが重要です。
医療システムの開発費用に影響する主な要素は以下のとおりです。
- 必要な機能数と種類
- 医療専門知識の要求度
- システム形態とライセンス形式
- 要件定義の明確さと変更頻度
- データ移行の規模と複雑さ
必要な機能数と種類
医療システムに実装する機能の数と種類は、開発費用に大きく影響します。
シンプルな患者管理だけのシステムと、電子カルテ・レセプト処理・検査オーダー・処方箋発行など多機能なシステムでは、当然後者の方が開発工数が増えるため費用も高くなります。
一般的には、以下のような機能を追加するごとに開発費用は増加していきます。
- 患者基本情報管理:基本機能として比較的低コスト
- 予約管理システム:中程度のコスト増
- 電子カルテ機能:高コスト(特に医療専門性が高い部分)
- 診療報酬請求(レセプト)機能:高コスト(制度対応が必要)
- 検査・処方オーダリング:高コスト(外部機器連携が必要)
- 医療画像管理(PACS連携):非常に高コスト
例えば、基本的な患者管理機能だけなら60万円程度からのノーコード開発も可能ですが、フル機能の電子カルテシステムとなると300万円以上が相場となります。
 大熊滉希
大熊滉希重要なのは、本当に必要な機能を見極めること。
すべての機能を最初から実装するのではなく、段階的に機能を追加していくアプローチも費用を抑える有効な方法です。
医療専門知識の要求度
医療システムの開発には、一般的なシステム開発のスキルだけでなく、医療に関する専門知識も必要となります。
特に以下のような要素が専門性を高め、開発費用を押し上げる要因となります。
- 診療科特有の用語や業務フローへの対応
- 医療保険制度やレセプト処理の複雑なルール対応
- 医療安全に関わる各種チェック機能の実装
- 医療機器との連携やデータ形式の変換
専門性が高いシステムになるほど、開発に携わるエンジニアやコンサルタントの人月単価も高くなります。
 大熊滉希
大熊滉希一般的なシステム開発では、エンジニアの月額単価が40万円〜80万円程度なのに対し、医療専門知識を持つエンジニアの場合は80万円〜160万円程度と2倍近い差があることも。
開発するシステムの専門知識のレベルで大きく開発費用が変わることは念頭に置いておきましょう。
システム形態とライセンス形式
医療システムの形態やライセンスの形式によっても、開発費用は大きく変わります。
システム形態による違い
- オンプレミス型:初期費用が高い(200万円〜500万円)が、長期的に見ると月額費用が安定
- クラウド型:初期費用が低い(10万円〜数十万円)が、月額費用が継続的に発生
ライセンス形式による違い
- クライアントライセンス(端末数に応じた課金)
- ユーザーライセンス(利用者数に応じた課金)
- 病床規模別ライセンス(病院の規模に応じた課金)
特に注意すべきは、医療機関の規模に合わないライセンス形態を選んでしまうと、無駄なコストが発生することです。
例えば小規模クリニックが、大規模病院向けの包括的なライセンス体系を選んでしまうと、使わない機能のコストまで負担することになります。
 大熊滉希
大熊滉希レセプトコンピューター(レセコン)との連携方法も重要なポイントです。
レセコン一体型の電子カルテシステムは初期費用が高い(450万円前後)ですが、別々のシステムを連携させる手間やリスクを避けられるメリットがあります。
要件定義の明確さと変更頻度
システム開発において、要件定義の明確さと開発途中での変更頻度は、最終的な開発費用に大きく影響します。
開発開始時点での要件が曖昧だと、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 開発途中での認識の食い違いによる手戻り
- 想定外の機能追加による追加コスト
- テスト工程の長期化による工数増加
- リリース後の修正対応の増加
特に医療現場では、実際に使ってみないと分からない業務上のニーズがあることも多く、要件の変更が発生しやすい傾向があります。
当初の見積もりでは100万円だったプロジェクトが、変更対応のために最終的に150万円になるケースも珍しくありません。
変更による影響を最小限に抑えるには、以下のようなアプローチが効果的です。
- プロトタイプを早めに作成して、実際の業務フローに合うか確認する
- 現場スタッフを要件定義段階から巻き込む
- 重要度の高い機能から段階的に開発・リリースしていく
 大熊滉希
大熊滉希ノーコード開発ツールを活用すれば、プロトタイプの作成や変更対応を低コストで実施できるため、要件の不明確さによるリスクを軽減できます。
データ移行の規模と複雑さ
既存の紙カルテや別システムからのデータ移行の規模と複雑さも、開発費用に大きく影響します。
特に長年蓄積された患者データを新システムに移行する場合、予想以上のコストがかかることがあります。
データ移行に影響する主な要素は以下のとおりです。
- 移行対象レコード数(患者数、診療記録数など)
- データフォーマットの複雑さ(構造化されていないデータの変換)
- データクレンジングの必要性(不整合データの修正)
- 過去データの移行期間(全データか、直近数年分のみか)
例えば、小規模クリニックの1,000人程度の患者データであれば10万円〜30万円程度で移行可能ですが、大規模病院の数万人規模のデータ移行になると100万円以上かかることも珍しくありません。
医療システムの開発費用を安く抑えるコツ
医療システムの導入は、医療機関の業務効率化や患者サービス向上に大きく貢献しますが、費用面での懸念もあると思います。
限られた予算の中で最大の効果を得るためには、開発費用を賢く抑えるコツを知っておくことが重要です。
医療システムの開発費用を安く抑えるコツは以下のとおりです。
- ノーコードで開発する
- 必要な機能に絞って段階的に導入する
- 医療システム開発の実績豊富な会社を選ぶ
- クラウド型システムを検討する
- 補助金・助成金を活用する
ノーコードで開発する
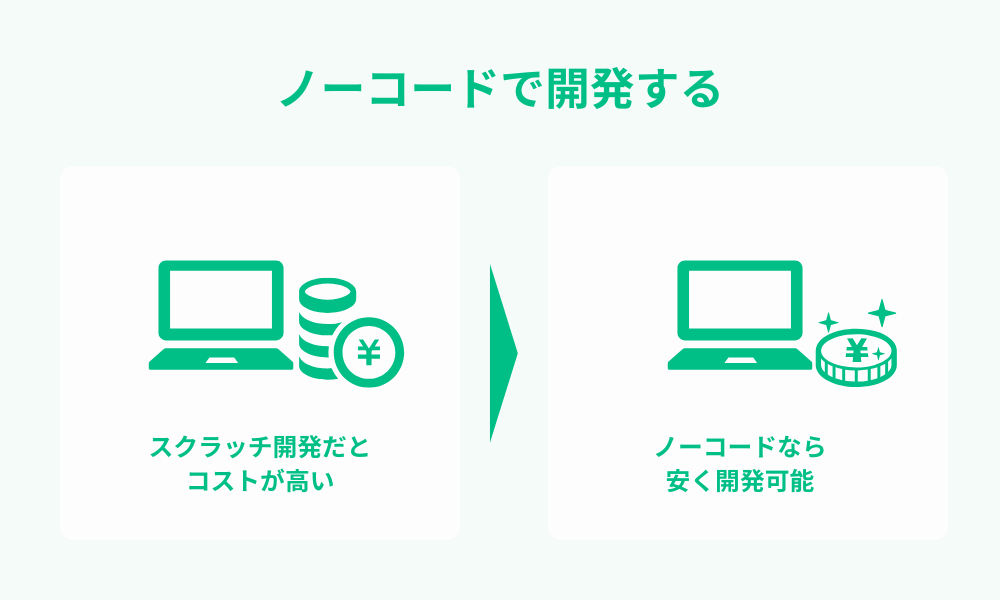
最も効果的に開発費用を抑える方法は、ノーコード開発を活用することです。
従来のスクラッチ開発(一からプログラミングで作成)と比較すると、以下のようなメリットがあります。
- 開発費用が1/3〜1/4程度に抑えられる
- 開発期間が大幅に短縮される(数ヶ月→数週間)
- 仕様変更や機能追加が比較的容易
- 医療関連のテンプレートが用意されている場合も多い
例えば、患者管理や予約システムなどの基本機能であれば、ノーコード開発ツールで十分実現可能です。
ノーコードツールは近年機能の充実が進んでおり、、簡易的な電子カルテシステムの構築も可能になっています。
ただし、非常に専門的な機能や他システムとの複雑な連携が必要な場合は、ノーコードだけでは対応できないこともあります。
 大熊滉希
大熊滉希ノーコードで全ての対応が難しい場合でも、基本機能はノーコードで開発し、専門的な部分だけカスタム開発するハイブリッド開発で、全体としての費用を抑えることができます。
必要な機能に絞って段階的に導入する
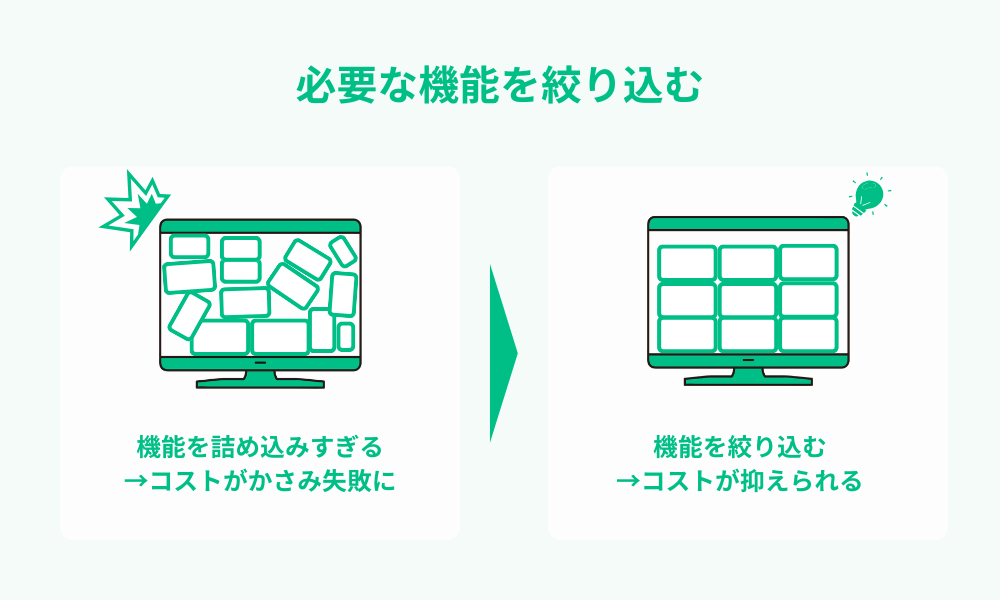
医療システムには様々な機能が搭載可能ですが、すべての機能を一度に導入する必要はありません。
必要最低限の機能から始めて、段階的に機能を拡張していく方法が費用対効果の高いアプローチです。
例えば、以下のような段階的導入が考えられます。
第1段階(基本機能)
- 患者基本情報管理
- 予約管理システム
- 簡易的な会計処理
第2段階(業務効率化)
- 電子カルテの基本機能
- 処方箋発行システム
- レセプト処理機能
第3段階(高度機能)
- 医療機器との連携
- 他医療機関とのデータ連携
- 診断支援システム
このように段階を踏むことで、初期費用を抑えつつ、実際の運用状況に合わせて必要な機能だけを追加できます。
また、一度に多くの変更を行わないため、医療スタッフの負担も軽減されるという副次的効果もあります。
具体的な機能選定にあたっては、「これがなければ業務が回らない」という必須機能と、「あれば便利だが必須ではない」という機能を明確に区別することが重要です。
 大熊滉希
大熊滉希優先度の高い機能から順に導入していくことで、現場で本当に必要な機能のみを実装していくことができるので、無駄な開発費用を削減できます。
医療システム開発の実績豊富な会社を選ぶ
一見すると費用が高く感じられるかもしれませんが、医療システム開発の実績が豊富な会社に依頼することは、結果的に費用を抑えることにつながります。
その理由は以下のとおりです。
- 見積もりの精度が高く、後から想定外の追加費用が発生するリスクが低い
- 医療現場特有の要件を理解しているため、開発の手戻りが少ない
- 開発スピードが速く、短期間で導入できるため人件費が抑えられる
- 過去の開発資産やテンプレートを活用できるため、一から開発するよりも効率的
 大熊滉希
大熊滉希特に医療システムは患者情報を扱う重要なシステムであるため、信頼性やセキュリティ面でのノウハウも重要です。
安さだけを重視して経験の浅い開発会社に依頼すると、運用開始後のトラブル対応やセキュリティ問題で結局余計なコストがかかることも少なくありません。
クラウド型システムを検討する
医療システムには大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。初期費用を抑えたい場合は、クラウド型システムの採用を検討する価値があります。
クラウド型のメリット(費用面)
- 初期費用が大幅に安い(10万円〜数十万円程度)
- サーバー機器の購入・設置が不要
- 保守・メンテナンス費用が月額料金に含まれることが多い
- スケーラビリティが高く、規模拡大時の追加コストが明確
- システムアップデートが自動的に行われる場合が多い
例えば、オンプレミス型の電子カルテシステムでは初期費用が200万円〜500万円程度かかるのに対し、クラウド型では初期費用10万円〜数十万円程度で導入できるケースが多いです。
ただし、月額料金が継続的にかかるため、長期的に見ると総コストがオンプレミス型を上回る可能性もあります。
一般的には、5年程度の利用を想定した場合の総コストで比較検討することをおすすめします。
 大熊滉希
大熊滉希クラウド型はインターネット回線に依存するため、安定した高速回線の確保が必要である点や、一部の専門的な機能がクラウド型では提供されていない場合もあるため、導入前に自院の要件との適合性を確認することが重要です。
補助金・助成金を活用する
医療システムの導入には、様々な公的補助金や助成金を活用できる可能性があります。
これらを上手に活用することで、実質的な導入費用を大幅に抑えることができます。
主な補助金・助成金制度
- IT導入補助金
- 中小企業や小規模事業者のITツール導入を支援
- 医療機関も条件を満たせば申請可能
- 補助率は1/2〜2/3、上限額は最大450万円程度(年度により変動)
- 地域医療介護総合確保基金
- 各都道府県が実施する医療ICT化支援事業
- 地域によって支援内容や金額が異なる
- 医療機関向けデジタル化支援補助金
- 厚生労働省が実施する場合がある
- オンライン資格確認や電子カルテの導入支援など
 大熊滉希
大熊滉希補助金・助成金は申請期間や予算枠が限られていることが多いため、導入計画を立てる際には早めに情報収集を行い、申請に必要な準備を整えておくことが重要です。
医療システムの見積もりの妥当性を調べる方法
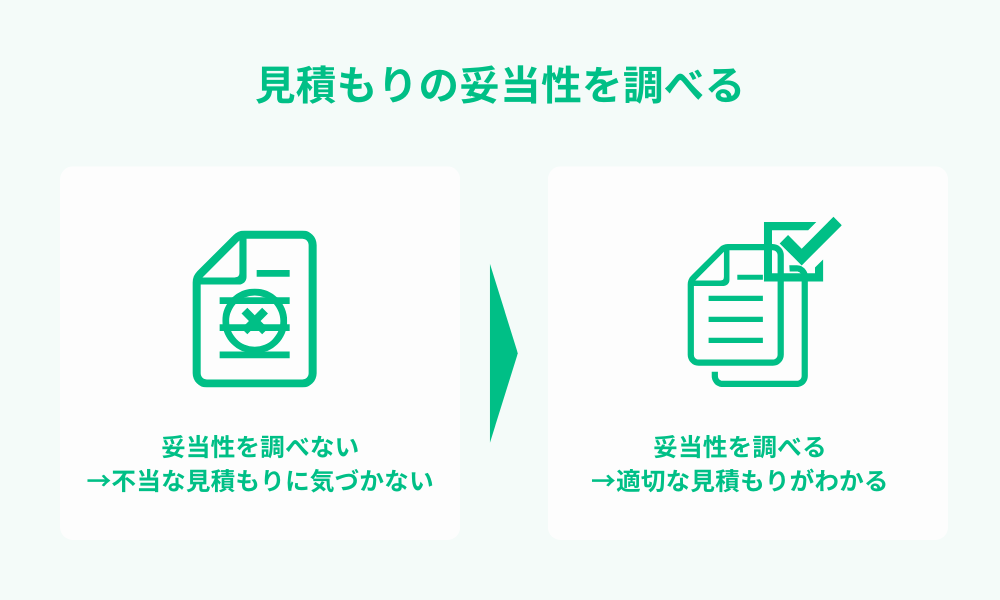
医療システムの見積もりが適正かどうかを判断するためには、以下の方法が効果的です。
- 複数の開発会社から見積もりを取得して比較する
- 同規模・同業種の医療機関に導入費用を聞いてみる
- 見積書の内訳を詳細に確認し、不明点は質問する
- 業界団体や医療情報学会などが公表している費用相場を参照する
- IT導入補助金などの申請用資料にある標準価格と比較する
特に重要なのは複数社からの見積り取得です。
同じ要件でも、会社によって30%以上価格差があることも珍しくありません。
また、見積書の内訳を詳細に確認し、「その他」や「諸経費」などの曖昧な項目が多すぎる場合は要注意です。
 大熊滉希
大熊滉希具体的な作業内容や成果物を明確にすることで、後からの追加費用発生リスクを減らせます。
医療システム開発会社の選び方
医療システムは一般的なシステムと異なり、医療特有の知識や経験が必要です。
最適な開発会社選びのポイントを解説します。
医療システムの開発実績があるか
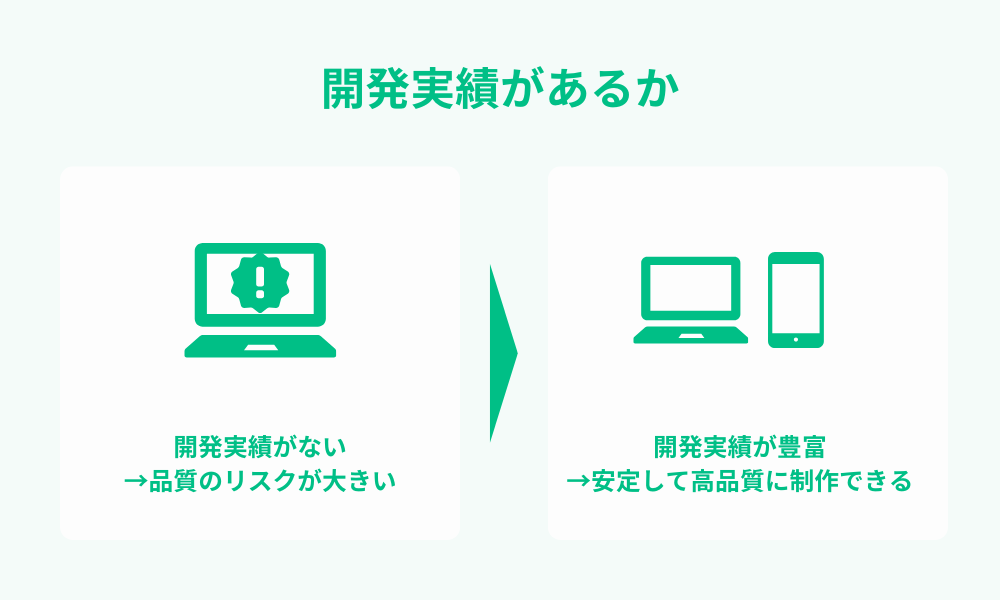
医療システム開発の実績がある会社を選ぶことは非常に重要です。
医療分野には独特の業務フローや規制があり、それらを理解していない開発会社では、使い勝手の悪いシステムになるリスクがあります。
チェックポイント
- 過去に開発した医療システムの種類と数
- 自院と同規模・同診療科の医療機関への導入実績
- 医療関連の法規制や標準規格への対応経験
 大熊滉希
大熊滉希実績を確認する際は、導入事例や具体的な成功例を詳しく聞くことが大切です。
実績を具体的に確認することで、開発会社の経験が、自分たちの開発したいシステムに活かせそうなのかという部分を判断することができます。
セキュリティ対策の充実度
医療システムは患者の機密情報を扱うため、高いセキュリティレベルが求められます。
特に2023年4月からは医療機関へのサイバーセキュリティ対策が義務化されているため、セキュリティに強い開発会社を選ぶことが重要です。
チェックポイント
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の取得
- プライバシーマークなどのセキュリティ関連認証の有無
- データ暗号化やアクセス制御などのセキュリティ対策
- セキュリティインシデント発生時の対応体制
 大熊滉希
大熊滉希開発会社自身のセキュリティ対策だけでなく、開発するシステムにどのようなセキュリティ機能を実装できるかも重要なポイントです。定期的なセキュリティ診断やアップデート対応が可能かどうかも確認しておきましょう。
導入後のサポート体制
医療システムは導入して終わりではなく、長期間にわたって使用し続けるものです。
そのため、導入後のサポート体制が整っているかどうかは非常に重要な選定基準となります。
チェックポイント
- サポート対応時間(平日のみか、夜間・休日対応があるか)
- 障害発生時の対応フロー(復旧までの目標時間など)
- 保守契約の内容と料金体系
- スタッフ向けの研修・マニュアル提供
- 医療制度改正時のアップデート対応
 大熊滉希
大熊滉希特に医療現場では、システムダウンが直接患者ケアに影響する可能性があるため、迅速なトラブル対応が可能な体制が整っているかどうかを確認することが重要です。
また、頻繁に行われる診療報酬改定などへの対応も、システムの長期運用には欠かせない要素です。
開発担当者の意思疎通能力
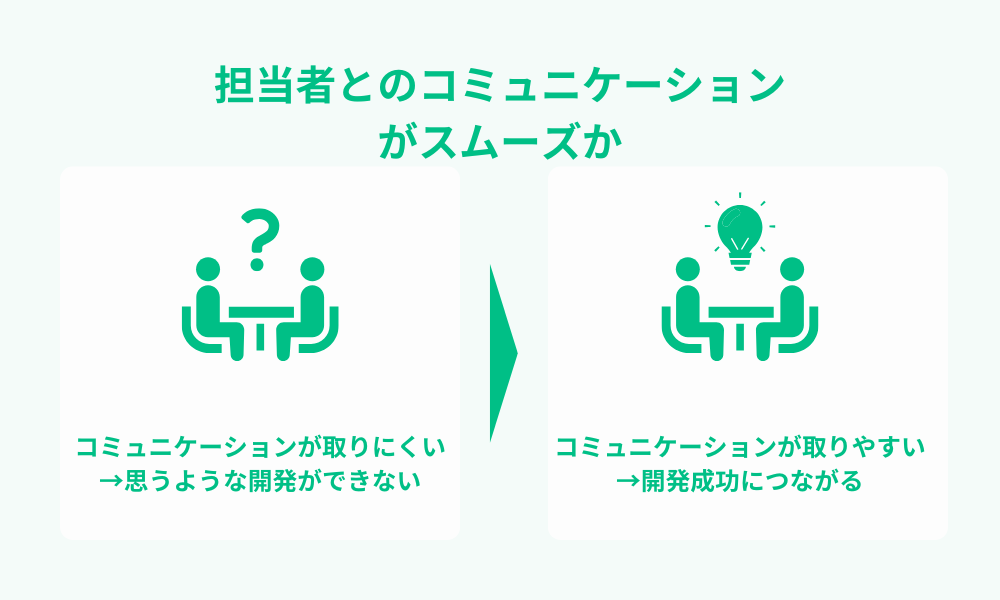
システム開発においては、開発会社とのスムーズなコミュニケーションが取れることが非常に重要です。
コミュニケーションに問題があると、以下のようなリスクが生じます。
- 医療現場の実際の業務フローを反映できない
- 要望が正確に伝わらず、想定と異なるシステムになる
- 開発途中での仕様変更が増え、コストや納期に影響する
チェックポイント
- 医療用語や業務を理解しているか
- 質問や要望に対して迅速・的確に回答できるか
- 打ち合わせの議事録や仕様書が明確で理解しやすいか
- 専門用語を使いすぎず、わかりやすく説明できるか
 大熊滉希
大熊滉希初回の打ち合わせや見積もり段階でのやり取りは、その後の開発にもつながってくる部分です。
この段階で違和感を覚えたり、説明が理解しづらかったりする場合は、本格的な開発段階でも同様の問題が発生する可能性が高いため、注意が必要です。
医療システムを格安で開発するならEPICs
EPICs株式会社は、BubbleやAdaloなどのノーコードツールに特化したプロフェッショナル集団として、日本最大級の開発実績を誇るノーコード開発会社です。
多くの企業様にご依頼をいただき、これまで100件を超えるアプリ・システムを開発してきました。
患者管理システム、予約管理システム、簡易電子カルテなど、医療現場に必要なシステムを短期間で開発し、医療スタッフが操作のしやすいデザインと、患者情報を守る強固なセキュリティ対策を実現します。
また弊社は、企画から設計、開発、そして導入後のサポートまで一貫して対応しております。
定期的なアップデート、トラブル時の迅速対応など、導入後のサポート体制も万全です。
「どんなシステムが必要か分からない」「予算に合うか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
お客様の予算と希望に合わせた最適なプランをご提案します。
1からの開発も、途中からの開発も、お気軽にEPICsにご相談ください!